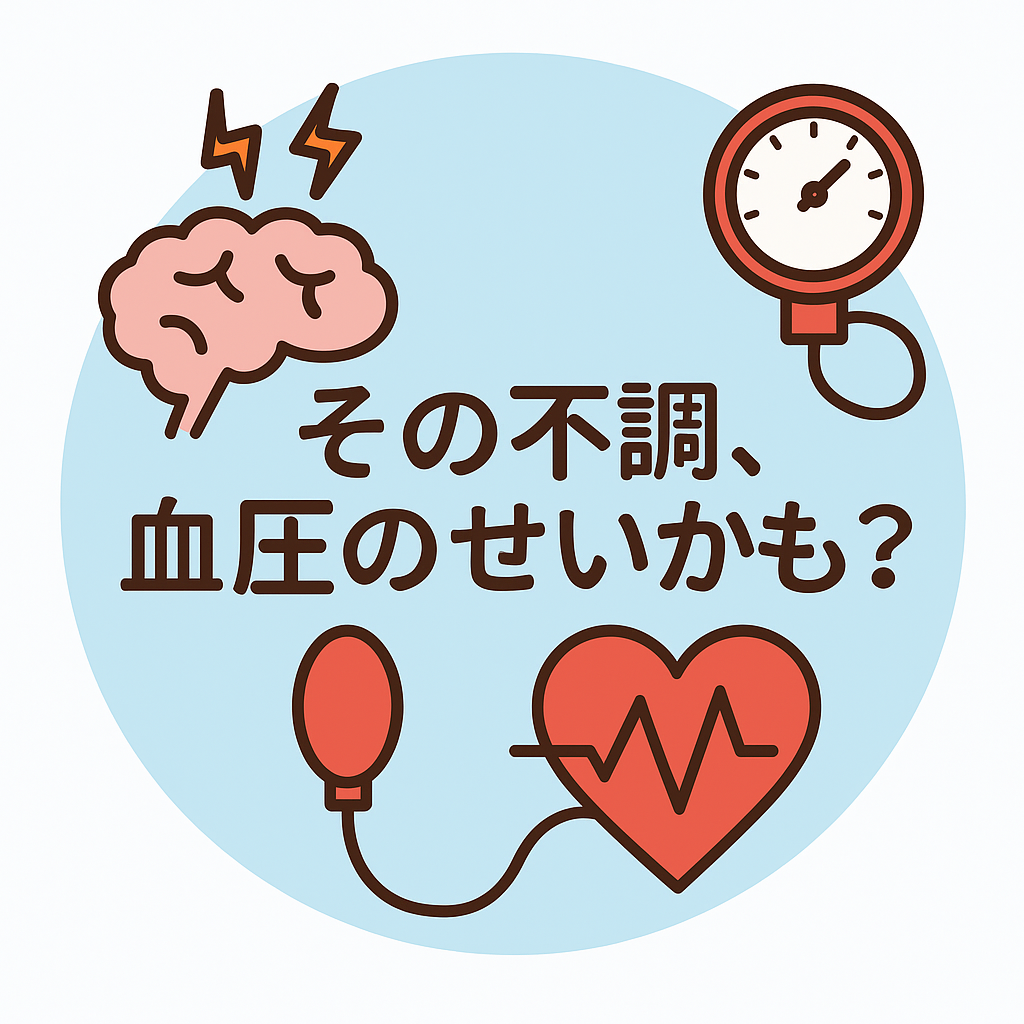高血圧の原因とは?年齢・遺伝・生活習慣の関係を徹底解説
「最近、血圧が高めって言われたけど、なぜ上がるのか分からない…」
そんな疑問を持っている方は少なくありません。
高血圧は日本人の生活習慣病の中でも特に多く、年齢を重ねるほどそのリスクは高まります。しかし、実は遺伝や性格、ストレス、食習慣など、さまざまな要因が関わっていることをご存じでしょうか?
この記事では、薬剤師の視点から、高血圧の原因についてやさしく丁寧に解説します。
加齢や遺伝の影響がどこまであるのか?
自分で変えられる生活習慣とは何か?
本記事を読めば、自分の血圧上昇の原因に気づき、日常生活の中でできる対策が見えてくるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
高血圧とは何か?基本的な仕組み
血圧とは、心臓から送り出された血液が血管の壁を押す力のことを指します。
この圧力が常に高い状態が続いていると、「高血圧」と診断されます。
具体的には、以下の数値が基準とされています:
- 収縮期血圧(上の血圧):140mmHg以上
- 拡張期血圧(下の血圧):90mmHg以上
このような状態が慢性的に続くと、心臓や脳、腎臓などに大きな負担をかけることになり、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などの重大な病気につながる恐れがあります。
高血圧の怖いところは、自覚症状がほとんどない点です。
そのため、健康診断などで指摘されるまで気づかず、「気づいた時には進行していた」というケースも少なくありません。
では、どうして血圧が上がってしまうのでしょうか?
次の章では、具体的な原因について詳しく見ていきましょう。
高血圧の主な原因とは?
高血圧には明確なひとつの原因があるわけではなく、多くの場合、いくつかの生活習慣や体質的な要因が重なって起こると考えられています。
ここでは、主な原因を5つに分けてご紹介します。

1. 塩分の過剰摂取
日本人の食生活は塩分が多い傾向にあります。ナトリウム(塩分)を多く摂ると、血液中の水分量が増え、血管にかかる圧力が上がるため、血圧が上がりやすくなります。
WHOの推奨では、1日の塩分摂取目安は5g未満ですが、日本人の平均はその倍以上とも言われています。
2. 運動不足
適度な運動は血管をやわらかく保ち、血液の循環を助ける働きがあります。しかし、長時間のデスクワークや運動習慣の欠如によって血流が悪くなると、血圧が上がりやすくなります。
3. 喫煙・過度な飲酒
タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させる作用があり、一時的に血圧を急上昇させる原因になります。また、アルコールも飲みすぎると交感神経を刺激して血圧を上昇させる可能性があります。
4. ストレス

ストレスを感じると、体は自律神経を介して血圧を上げる反応を示します。慢性的なストレス状態が続くと、常に血圧が高めになってしまう恐れがあります。
5. 肥満・内臓脂肪
内臓脂肪が多いと、血管に負担がかかりやすくなり、インスリン抵抗性などを通じて血圧を上昇させる要因になります。特にお腹周りの脂肪が多い方は要注意です。
これらの生活習慣要因は、改善することで血圧を穏やかに保つ手助けが期待できます。次の章では、年齢と血圧の関係について詳しく解説します。
年齢と血圧の関係|なぜ加齢で上がるのか?
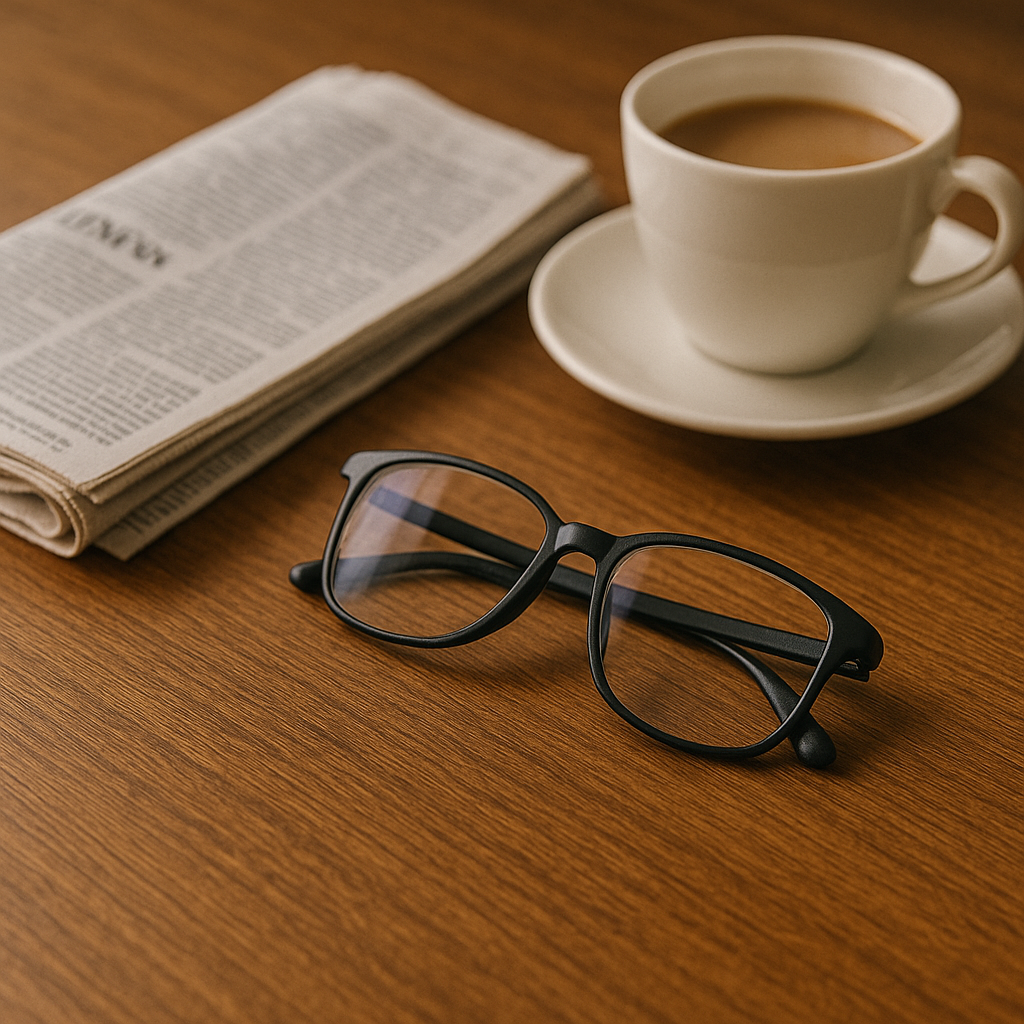
年齢を重ねると、誰でもある程度は血圧が上がってくる傾向があります。日本人の約6割以上が60歳以上で高血圧と診断されているという調査もあるほどです※1。
では、なぜ加齢とともに血圧が高くなるのでしょうか?
1. 血管の柔軟性が失われる
年齢を重ねると、血管は少しずつ弾力性を失い、硬くなっていきます(動脈硬化)。その結果、心臓が血液を送り出す際の抵抗が大きくなり、血圧が上がります。
2. 腎臓機能の低下
加齢により腎機能が低下すると、体内のナトリウム(塩分)や水分の調整がうまくいかなくなり、血圧が上昇しやすくなります。
3. ホルモンバランスの変化
加齢に伴って、血圧調節に関与するホルモンの分泌や反応が鈍くなることが知られています。特に女性では更年期以降、血圧が急に上がるケースも見られます。
4. 加齢による運動量や代謝の低下
年を重ねると運動量が減り、基礎代謝も落ちてくるため、体重が増加しやすくなり、それに伴って血圧も上がりやすくなります。
つまり、年齢に伴う血圧上昇は自然な変化ではありますが、「年のせいだから仕方ない」と放置せず、生活習慣を意識することが重要です。
次に、もうひとつの注目すべき要因である「遺伝」について見ていきましょう。
※1 参考:厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査結果」
遺伝との関係|家族に高血圧が多いとどうなる?
「親も高血圧だったから、自分もそうなるのでは…?」
そう心配される方も多いと思います。
結論から言うと、高血圧はある程度“遺伝の影響”を受ける病気です。
実際、両親のどちらかが高血圧の場合、子どもが高血圧になるリスクは約2倍になるという研究報告もあります※2。
1. 遺伝的に受け継がれやすい体質
高血圧になりやすい体質には、以下のような特徴があります:
- ナトリウム(塩分)感受性が高い
- 血管が収縮しやすい(交感神経が優位)
- 腎機能が弱く、ナトリウム排出能力が低い
これらは遺伝的要因として引き継がれる可能性があります。
2. 環境的な要因も大きい
ただし、遺伝だけではなく、家族内での食事習慣や生活スタイルも似ていることが多いため、「遺伝+生活習慣」がセットになっていることが多いのです。
例えば、塩辛いものが好き・運動しない・夜更かしといった生活スタイルも、親から子へ「環境として」引き継がれるケースがあります。

3. 遺伝の有無に関係なく予防は可能
遺伝的なリスクがあったとしても、生活習慣を整えることで高血圧を予防・改善することは十分に可能です。
特に若いうちから血圧を意識し、食事や運動に気を配ることが将来の健康を守る鍵となります。
※2 参考:日本高血圧学会「高血圧と遺伝の関係に関する研究報告」
まとめ
高血圧は、誰にでも起こり得る身近な健康課題です。
原因はひとつではなく、塩分の摂りすぎ・運動不足・喫煙・ストレス・肥満・加齢・遺伝など、さまざまな要素が複雑に関係しています。
中でも、生活習慣の改善は、自分で取り組める予防・対策の鍵です。
- まずは食事を見直す(減塩・カリウムを意識)
- 無理のない運動習慣をつける
- ストレスをためない生活を意識する
また、家族に高血圧の方がいる場合でも、日々の意識でリスクを抑えることができます。
「自分はまだ大丈夫」と思わず、早いうちから血圧を意識した生活を始めてみましょう。
参考文献・出典
- 厚生労働省「e-ヘルスネット」:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/
- 令和元年「国民健康・栄養調査報告書」
- 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」
- 日本循環器学会「高血圧と生活習慣に関するレビュー」
※本記事は薬剤師の視点から健康情報を提供するものであり、特定の疾患の診断・治療を目的としたものではありません。気になる症状がある場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
この記事を書いた人 Wrote this article
アラサー薬剤師 研修認定薬剤師
みなさんこんにちは! このサイトを運営しているアラサー薬剤師と申します。 現在はとある調剤薬局で管理薬剤師をしております。 このサイトでは将来生活習慣病で困ることの無いように、今からできる対策などについて情報発信していきます。 薬剤師歴8年 研修認定薬剤師4年目 学校薬剤師3年目 休日夜間急病センター4年目