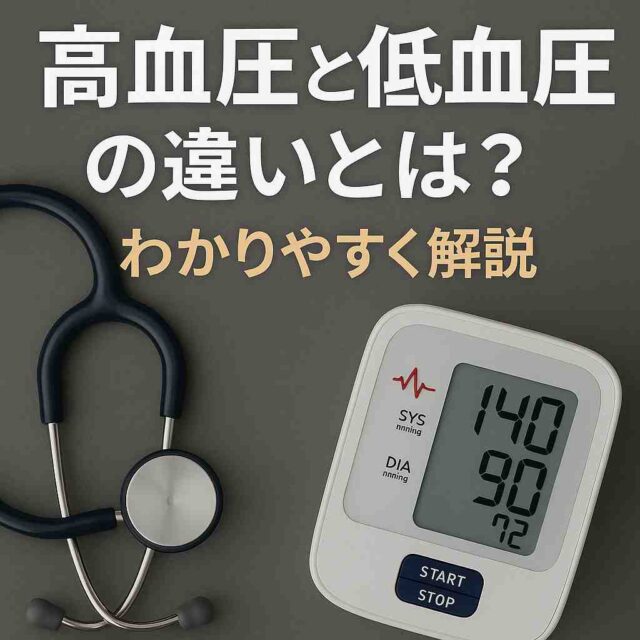「高血圧」と聞くと、中高年以降の疾患というイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし近年では、20代・30代といった若年層の間でも高血圧が増加傾向にあることが報告されています。
しかも、若いからこそ「自覚がない」「病院に行くほどではない」と判断されやすく、発見が遅れやすいという現状も見逃せません。
本記事では、若年層における高血圧の特徴や背景、そしてその対策について、薬剤師の視点から丁寧に解説いたします。

若年層における高血圧:なぜ増えているのか?
20代・30代の高血圧は「例外」ではない
厚生労働省の調査によると、20代・30代男性のおよそ10〜15%、女性でも5〜10%が「収縮期血圧140mmHg以上」または「拡張期血圧90mmHg以上」のいずれかに該当しており、医学的には高血圧と診断されるレベルに達していることが示されています。
これは決して少数派ではなく、若年層でも血圧に対する注意が必要であることを意味しています。
現代型高血圧の背景:生活習慣の変化
20代・30代の高血圧には、以下のような「現代的なライフスタイル」に起因する要素が多く関与しています。
- 長時間のデスクワーク:身体活動量が少なく、血流の停滞が起きやすい。
- 高塩分・高脂肪の外食中心の食生活:特にコンビニやファストフードに依存しやすい。
- 慢性的なストレス:仕事や人間関係、SNS疲れなどにより自律神経が乱れる。
- 睡眠不足・不規則な生活:ホルモンバランスを崩し、血圧調節に影響。
これらはすべて、高血圧の主要な危険因子として知られており、「若さゆえに大丈夫」と考えていると、後々深刻な健康リスクに繋がる可能性があります。
「若年性高血圧」はなぜ見過ごされやすいのか?
高血圧の初期段階では、特別な自覚症状が出にくいことが多く、「頭が重い」「疲れやすい」といった些細な症状も、日々のストレスや睡眠不足のせいにされがちです。
さらに、定期的な健康診断を受けていない若年層も多いため、実際には高血圧であっても未診断のまま放置されているケースも少なくありません。
こうした背景から、若年性高血圧は「静かなるリスク」とも呼ばれており、早期の対応が求められます。
若年性高血圧の原因とメカニズム

1. 遺伝的要因と体質
家族に高血圧の人がいる場合、その遺伝的傾向が影響することが知られています。
特に両親のいずれか、あるいは両方が高血圧の場合、子どもも高血圧を発症するリスクが高まるというデータがあります。
また、塩分に対する感受性が高い体質の人は、同じ量の塩分を摂取しても血圧が上がりやすい傾向にあるため、遺伝体質を意識した生活管理が必要です。
2. 食生活の乱れ
20〜30代は仕事や交友関係が活発になる時期であり、外食やコンビニ食が日常的になる人も多いでしょう。
これらの食事は高塩分・高脂肪であることが多く、野菜や果物などのカリウム摂取が不足しがちです。
特に塩分の過剰摂取は、血管内のナトリウム濃度を上昇させ、血液量の増加により血圧を高める直接的な要因となります。
3. 運動不足と身体活動量の低下
仕事で長時間パソコンに向かう、通勤時間が長く座って過ごすといった生活習慣は、明確に血圧上昇と関連しています。
適度な運動は、血管の柔軟性を保ち、交感神経の過剰な興奮を抑える作用があります。
逆に運動不足が続くと、血流が悪くなり、血管抵抗が高まることで高血圧を引き起こしやすくなります。
4. 慢性的ストレスと自律神経の乱れ
ストレスがかかると、交感神経が優位になり、心拍数や血圧が上昇しやすくなります。
仕事、学業、人間関係といった日常的なプレッシャーが慢性的に続くと、自律神経のバランスが崩れ、高血圧が慢性化する危険性があります。
さらに、ストレス解消のための喫煙や過度な飲酒も、血管にダメージを与え、血圧上昇を助長します。
5. 睡眠の質の低下
質の高い睡眠は、血圧を正常に保つ上で非常に重要です。
慢性的な睡眠不足や、睡眠の質が悪い状態(例えば、深く眠れていない、夜中に何度も目が覚める)では、夜間に十分な血圧の低下が得られず、翌朝の血圧が高くなる「早朝高血圧」を引き起こしやすくなります。
これが繰り返されることで、常に高めの血圧状態が続くようになってしまうのです。
若年性高血圧が引き起こす健康リスク
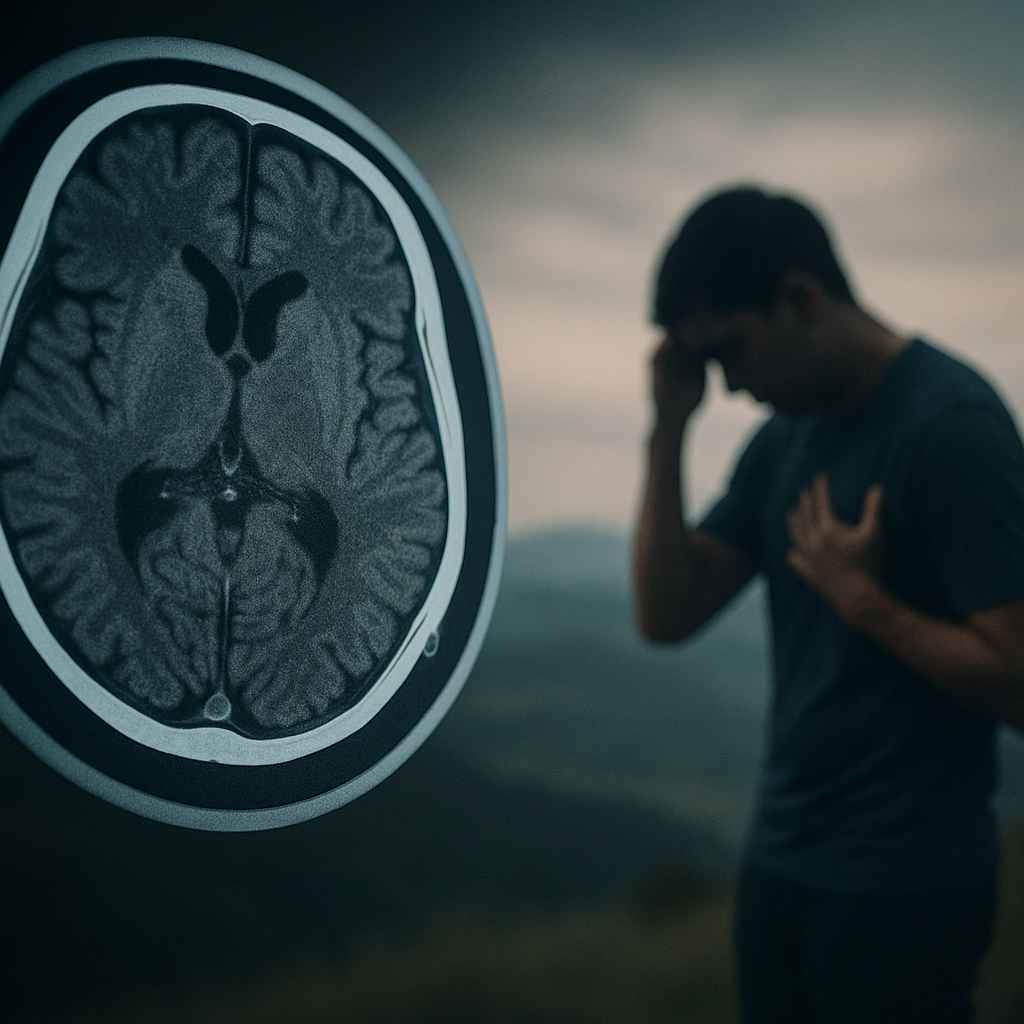
高血圧は「沈黙の病」
高血圧は自覚症状が乏しく、長期間にわたって放置されやすい病気であることから、「サイレントキラー(沈黙の殺し屋)」と呼ばれることがあります。
特に若年層では、健康への意識が高くないケースも多く、「まだ大丈夫」と放置されることが多いため、注意が必要です。
脳卒中や心疾患のリスクが高まる
高血圧状態が続くと、血管に常に圧力がかかり、血管壁が厚く硬くなる「動脈硬化」が進行します。
その結果、脳梗塞や脳出血、心筋梗塞など、命に関わる重大な疾患を引き起こすリスクが高まります。
若年性高血圧であっても、その状態が長く続くことで、40代・50代に深刻な合併症を抱えるケースが少なくありません。
腎臓への影響と慢性腎臓病(CKD)
腎臓は血液中の老廃物をろ過する臓器であり、その機能は非常に繊細です。
高血圧が続くと腎臓の細い血管が損傷され、ろ過機能が低下することで「慢性腎臓病(CKD)」を発症するリスクが高まります。
CKDは初期にはほとんど症状がないため、高血圧によって進行する腎機能低下は見過ごされやすく、結果的に人工透析が必要になることもあります。
将来的な生活習慣病のリスク増加
高血圧は、糖尿病や脂質異常症と並ぶ「生活習慣病」の一つであり、これらの疾患は相互に悪影響を及ぼし合います。
高血圧に加えて血糖値やコレステロールの異常がある場合、心血管系へのリスクは飛躍的に高まります。
若いうちからこれらの状態に陥ることで、将来的な合併症のリスクが著しく増大します。
メンタルヘルスとの関連
高血圧があることで、「自分は健康ではないのでは」という不安やストレスを感じるようになる人もいます。
また、血圧の変動は自律神経に影響を及ぼし、不安障害やうつ症状を引き起こすこともあります。
身体の健康と心の健康は密接に関係しており、若年層の高血圧においてもメンタル面のケアは重要です。
今日からできる若年性高血圧の予防・改善法

1. 減塩を意識した食事管理
日本人の食塩摂取量は世界的に見ても多く、厚生労働省が推奨する1日あたりの塩分摂取量は男性7.5g未満、女性6.5g未満とされていますが、実際にはこれを超えている人が多数派です。
減塩の第一歩として、加工食品やインスタント食品、外食の頻度を減らし、家庭での調理で素材本来の味を活かす工夫が大切です。
また、減塩調味料やだしを活用することで、美味しさを損なわずに塩分を抑えることができます。
2. 毎日の運動習慣を取り入れる
運動は血管を柔軟に保ち、血圧を下げる効果があることが多くの研究で報告されています。
特にウォーキングや軽いジョギング、ストレッチ、ヨガなどの有酸素運動は、心肺機能を高め、自律神経の安定にも効果的です。
最初は1日15〜30分程度、週3〜5回を目安に取り入れるだけでも、体に変化を感じられるでしょう。
3. ストレスマネジメントを意識する
ストレスは高血圧の重要な要因です。
そのため、心の緊張を解きほぐす時間を意識的に作ることが、血圧管理には欠かせません。
音楽を聴く、趣味に没頭する、深呼吸や瞑想を取り入れるなど、自分に合ったリラクゼーション法を見つけましょう。
また、時には人に話すことも非常に効果的です。
4. 睡眠の質を高める工夫
睡眠の質を高めるには、「量」だけでなく「質」も重視する必要があります。
就寝前のスマホ使用やカフェインの摂取は控え、就寝・起床時間を一定に保つことで、体内リズムが整いやすくなります。
また、照明や室温、寝具などの環境整備も、睡眠の質を向上させる大切な要素です。

5. 定期的な血圧測定と医療機関の活用
若年層でも、家庭用血圧計を使って定期的に血圧をチェックすることが、早期発見・早期対処につながります。
「少し高めかな?」と思ったら自己判断せず、かかりつけの内科や循環器内科に相談することが大切です。
また、健康診断の結果をしっかり確認し、異常があれば速やかに受診するようにしましょう。
まとめ:若いうちからの血圧管理が未来を変える
若年層における高血圧は、決して「稀な症状」ではなく、現代社会のライフスタイルに密接に関係したリスクであることがわかっています。
その多くは、日々の生活習慣の中で改善・予防が可能なものであり、早い段階での気づきと行動が、将来の重大な健康リスクを回避する鍵となります。
「若いから大丈夫」と過信するのではなく、自分自身の身体と向き合い、今できることから少しずつ始めていくことが何より重要です。
本記事を通じて、20代・30代の皆様が高血圧に対する理解を深め、健やかな生活を送るためのきっかけとなれば幸いです。
参考文献・出典
- 厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」
- 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2024」
- オムロンヘルスケア「高血圧の症状・原因」
- 日本腎臓学会「慢性腎臓病(CKD)に関するガイドライン」
- 公益財団法人 生活習慣病予防協会「若年性高血圧の予防」
※本記事は薬剤師による情報提供に基づき作成しています。診断や治療は必ず医師の指示に従ってください。
この記事を書いた人 Wrote this article
アラサー薬剤師 研修認定薬剤師
みなさんこんにちは! このサイトを運営しているアラサー薬剤師と申します。 現在はとある調剤薬局で管理薬剤師をしております。 このサイトでは将来生活習慣病で困ることの無いように、今からできる対策などについて情報発信していきます。 薬剤師歴8年 研修認定薬剤師4年目 学校薬剤師3年目 休日夜間急病センター4年目